今回は肥満の人がなりやすい睡眠時無呼吸症候群(SAS)について紹介します。
大きな病気で生命の危険や運転中の事故などの原因にもつながりますので、睡眠時無呼吸症候群(SAS)をチェックし理解を深めましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、夜間、睡眠時に気道が虚脱し、閉塞したりに狭窄したりする病気です。これが原因で10秒以上の無呼吸は浅い呼吸が睡眠1時間あたり5回以上生じると睡眠時無呼吸と診断されます。
ここ50年で最も重要性が認識された疾病の一つで、日本人の成人男性の10人に1人いるといわれています。そして、だいたい256万人(人口約2%)の潜在患者がいるとされています。
こんな症状を感じませんか?

ちゃんと寝たつもりでも寝起きから頭痛、昼間に眠気やだるさ、熟睡感がない…誰もが感じる症状ですが複合的に感じたら医師に相談して下さい。
睡眠時無呼吸症候群になりやすい人
●肥満の人
●小さい顎
●首が太く短い
●アルコールが好き
●喉ちんこがが見えない
●舌と喉ちんこが近い
●扁桃腺肥大
睡眠時無呼吸症候群をチェック!
▢いびきがうるさいといわれる
▢呼吸が止まっているといわれる
▢夜中によく目が覚める
▢息苦しさで目が覚める
▢起きた時に頭痛がする
▢日中の眠気がひどい
▢高血圧の薬があまり効かない
▢起きた時口や喉が渇いている
▢集中力がすぐ低下する
▢熟睡感がない

睡眠時無呼吸症候群の3種類のタイプは?
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、主に次の3つのタイプに分けられます。
① 一番多い閉塞型睡眠時無呼吸
睡眠時無呼吸症候群で最も多いタイプで9割がこの閉塞型睡眠時無呼吸です
●原因:
寝ている時に舌や喉の周りの筋肉が緩んで呼吸の通り道を塞いでしまい呼吸が止まる
●特長:
・いびきが大きい
・肥満の人がなりやすい
・扁桃腺肥大の人
●メカニズム:
軌道は閉じているが胸とお腹で呼吸をしようと動いている

②指令障害の中枢型睡眠時無呼吸
肺や胸郭、呼吸に関わる筋肉、末端の神経には問題がなく呼吸中枢の機能障害によるものです。
●原因:
脳の呼吸中枢から指令する伝達が一時的に出なくなることによるもの
●特長:
・いびきが少ないことが多い
・脳の血管障害
・心不全
・モルヒネ系の薬を服用
●メカニズム:
軌道は開いているが呼吸するための筋肉が動かない事で呼吸ができない

③混合型睡眠時無呼吸
上記の①②の特徴が組み合わさったのが混合型睡眠時無呼吸
●原因:
閉塞型と中枢型が混在する
●特長:
・初期は中枢型から始まる
・後に閉塞型が合わさる
●メカニズム:
※①②を参照
内臓脂肪は首を太くし無呼吸に
内臓脂肪が原因で首回りに脂肪がつき、直接的に気道を狭くすることがあります。
その他横隔膜の上下運動の連動を妨げ呼吸が制限され、呼吸不全に影響を与える可能性があります。
脂肪細胞から分泌のレプチン
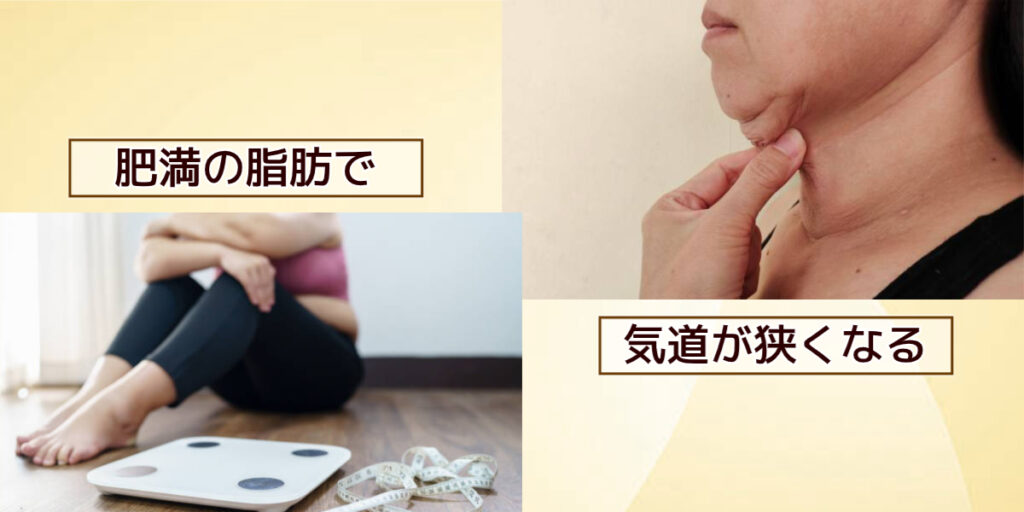
脂肪細胞から分泌されるレプチンには呼吸を調整する作用があります。内臓脂肪が過剰分泌するとレプチン抵抗性が起こります。
これが原因で低酸素血症や高二酸化炭素血症を発症する確率が高くなります。
無呼吸症候群による健康リスクなど
・動脈硬化
・高血圧
・心筋梗塞
・脳卒中
・糖尿病の悪化
・不整脈
・居眠り運転の事故

無呼吸症候群の検査方法は4種類
睡眠時無呼吸症候群の検査方法は以下の4種類に分かれます。
1-1問診、スクリーニング検査
お医者さんの問診により普段の生活習慣などを詳しく聞き取ります。
必要性があるなら簡易検査を行います。
問診ので症状のチェック
・いびきの有無
・いびきの大きさや頻度
・朝一の頭痛
・熟睡感の有無
・日中の眠気
・集中力の低下
・居眠り運転の有無
1-2簡易検査機器を使い検査
・自宅にて鼻や指にセンサーを装着し、酸素飽和度(SpO₂)や無呼吸の回数(呼吸の状態)を測定
・一晩のデータから「無呼吸低呼吸指数(AHI)」を算出して検査
2簡易ポリソムノグラフィー(簡易PSG)検査
1-2で無呼吸の症状が少しあったり検査の結果が不十分の場合は、簡易ポリソムノグラフィー(簡易PSG)検査を自宅にて行います。
・鼻カニューレ(呼吸流量)
・パルスオキシメータ(酸素飽和度)
・胸部・腹部バンド(呼吸運動)を使用
③精密ポリソムノグラフィー(PSG)
睡眠時無呼吸症候群を最も精密に検査することができます。今までは自宅で検査でしたが、精密ポリソムノグラフィーは病院にて検査を行います。
・脳波(睡眠段階の判定)
・眼球運動
・筋電図
・呼吸の量
・呼吸努力
・酸素飽和度
・心電図
・就寝時の姿勢
これらで無呼吸の種類の3つ(閉塞性・中枢性・混合性)や睡眠構造まで把握
④必要に応じて行う補助検査
・血液検査(甲状腺機能、糖代謝など)
・上気道の構造評価(内視鏡、CT、MRI)
・心臓機能検査(心エコー、24時間ホルター心電図)
無呼吸症候群の改善・治療方法
無呼吸症候群の改善、治療方法は上記の3つの症状や軽症、中小、重症によっても異なります。
①生活習慣の改善(軽度・中度)
●1体重を減らす…
食事をコントロールし、内臓脂肪や首まわりの脂肪を少なくすることで、狭くなった気道を元の広い状態に戻す
●2就寝時の姿勢改善…
仰向けで寝ると舌や軟口蓋が落ち、気道を狭く、塞ぐ原因になるので横向きで寝る工夫
●3アルコールや睡眠薬の制限…
アルコールや睡眠薬を飲むと喉の周りの筋肉を緩め舌が落ちやすくなります
●4喫煙をやめる…
喫煙は喉や鼻の粘膜に炎症を誘発させ気道の通りを悪くするので禁煙が必要
②CPAP(持続陽圧呼吸療法)

●CPAP(持続陽圧呼吸療法)は中度から重症の人に有効的です。
・世界的に無呼吸症候群の治療方法で一番利用されています
・即効性と実感できる効果が高い
・毎日の使用が必要になる
・睡眠時に鼻や口にマスクを装着し空気を軌道に強制的に送り込み、気道を確保して無呼吸を防ぐ方法
③口腔内装置(マウスピース)
・スリープスプリントともいう
・軽度から中度の症状に有効
・比較的効果が見込まれる
・下顎を前方に出す形で固定し上気道を広く確保
・専門の歯科医で作るとよい
・デメリットは顎関節や歯並びや装着時の違和感
④外科的手術(解剖的な狭窄が原因時)

●口蓋垂・軟口蓋・咽頭形成術(UPPP)…
・喉の余分な脂肪や組織、扁桃腺などを切除して気道を広げ確保
●舌根縮小術・顎骨前方移動術…
・舌やあごの位置を変えることにより気道を確保
●鼻の手術(鼻中隔矯正、下鼻甲介切除など)…
鼻の湾曲を矯正したり、粘膜の切除により鼻腔を広げ、鼻づまりを改善




